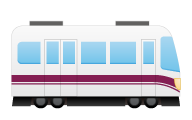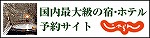この観光プランのおすすめポイント
 新潟でお寿司を食べよう
新潟でお寿司を食べよう
新潟のお寿司屋さんでは、聞いたことがない魚の名前が「今日のおすすめ」に張り出されています。
南蛮エビ、ノドグロ、ヤナギガレイなどは比較的ポピュラーですが、つづのめ、ゲンギョ、ドロエビ、ふなべた等となると???
これらは日本海近海で獲れる地魚で、新潟には多くの地魚が水揚げされます。
季節ごとに旬のネタを揃えていますので、新潟のお寿司屋さんに行ったら、まずは地魚を味わってみましょう。
新潟は、観光客相手の店が多い金沢よりも比較的リーズナブルな料金設定で、日本酒文化ですからお酒のアテになるような一品メニューも豊富。
豊かな海が育んだ新鮮な魚と新潟が誇るお米を使った銀シャリのコラボは最高です!
おすすめのお店はこちら おすすめの回転寿司はこちら
 新潟県の全93酒蔵の代表銘柄が大集合
新潟県の全93酒蔵の代表銘柄が大集合
新潟駅にある「ぽんしゅ館」は”越後・魚沼のドラマを食で語る”をコンセプトにした、新潟の豊かな自然や食文化を発信するテーマ型レストラン・ショップです。
新潟県内にある全蔵の酒を気軽に試飲できる「きき酒番所」のほか、呑み処や食事処、新潟の様々なお土産が買えるお店があります。
 きき酒は、受付で500円払い、お猪口とメダル5枚をもらってズラリと並んだ唎き酒マシーンから好きな地酒が試飲できるというもの。
きき酒は、受付で500円払い、お猪口とメダル5枚をもらってズラリと並んだ唎き酒マシーンから好きな地酒が試飲できるというもの。
気に入ったお酒は併設の酒販コーナーで買うことができます。
越後魚沼商店は、日本の伝統調味料、味噌、塩、醤油など、越後の食材・風土から生まれた新潟ならではのお土産を販売しています。
爆弾おにぎり家では、魚沼産コシヒカリを使った贅沢な大きいおにぎり、おかずにピッタリな惣菜を買うことができます。
ぽんしゅ館のホームページはこちら
 日本一の大地主”本間家”のエピソードなどが聞けます
日本一の大地主”本間家”のエピソードなどが聞けます
酒田の本間家は江戸時代3000町歩の田地を所有し、多くの小作人を雇っていました。
庶民の間では「本間様には及びはせぬが、せめてなりたや殿様に」と歌われたほどの財を成したといわれています。

 その本間家が藩主酒井家のために、幕府巡見使(将軍の代替りごとに特派された役人)用宿舎として建てた家屋が、本間家旧本邸として公開されています。
その本間家が藩主酒井家のために、幕府巡見使(将軍の代替りごとに特派された役人)用宿舎として建てた家屋が、本間家旧本邸として公開されています。
幕府巡見使が使ったあと、この建物はずっと本間家の人々が代々住んでいたのですが、案内の女性がその暮らしぶりや本間家が酒田に貢献したスケールの大きな話など、興味深い話をしてくれます。
本間家旧本邸のホームページはこちら
 酒田のシンボル的存在「山居倉庫」
酒田のシンボル的存在「山居倉庫」
山居倉庫は、明治時代に北前船に積み込む庄内米の積出港として栄えた酒田の歴史を今に伝える施設です。
明治26年に米の保管倉庫として建てられ、二重屋根にするなど風通しを良くする工夫を施した低温倉庫として、現在も使われています。
敷地内には酒田市観光物産館「酒田夢の倶楽」や庄内米歴史資料館、農産物直売所があり、観光客で賑わっています。
また、倉庫の裏側にあるケヤキ並木は、季節ごとにその美しい佇まいが変化し、絶好の撮影スポットになっています。
3月には、観光物産館「酒田夢の倶楽」にも雛人形が飾られます。
山居倉庫(酒田夢の倶楽)の詳しい情報はこちら
 庄内フレンチの名店 ル・ポットフー
庄内フレンチの名店 ル・ポットフー
酒田駅前にある、天才、佐藤久一がつくった開高健、山口瞳など数多くの食通に愛されてきたフレンチレストランです。
市場に揚がる庄内浜の新鮮な魚介類を、素材本来の旨みを活かす調理でおいしい料理に仕上げてくれます。
本格的なフレンチレストランの雰囲気のお店で、日本海の海の幸や山の幸をいただきましょう。
ル・ポットフーのホームページはこちら
※写真はイメージです。
 天童温泉
天童温泉
山形県のほぼ中央に位置する天童温泉。明治44年、田んぼの中に高温の源泉を掘り当てたのが、そのはじまりです。
泉質はナトリウム・カルシウム-硫酸塩温泉。
温泉街には三つの足湯も整備され、舞鶴山や市内に点在する施設めぐりなどとともに、のんびりとまち歩きが楽しめます。
天童温泉は、将棋のまちとしても知られています。
天童温泉の詳しい情報はこちら
※写真は「ほほえみの宿 滝の湯」の大浴場
 天童温泉屋台村「と横丁」
天童温泉屋台村「と横丁」
「天童温泉にかつての賑わいを取り戻したい!」そんな思いで天童温泉屋台村「と横丁」を設置しました。
「と横丁」という名前は、将棋駒の「歩兵」が敵陣に進入し成った時の「と金」に由来しています。「と横丁」に来ればどんな時でも元気になれる、という意味を込めました。

 「と横丁」には、天童・山形の食材を使った料理や地酒はもちろんのこと、自由に将棋が対局できるテーブルもご用意しております。
「と横丁」には、天童・山形の食材を使った料理や地酒はもちろんのこと、自由に将棋が対局できるテーブルもご用意しております。
地元の方も、天童温泉に旅行に来られた方も、気兼ねなく交流できる楽しい屋台村です。
※「と横丁」のホームページより引用
 美しい風景を船上から楽しもう
美しい風景を船上から楽しもう
松島は太古の昔、松島丘陵の一部が河川浸食によっていくつもの谷となり、さらに地殻変動によって海に沈降し、海面より高い部分が島として残りました。
その後、長い年月が凝灰岩(ぎょうかいがん)を浸食し、絶景の島々が誕生しました。
遊覧船に乗って「日本三景松島」湾内をめぐってみましょう。
松島の島々が織りなす美しい風景を船上から楽しむことができます。
松島遊覧船の詳しい情報はこちら

松島のシンボル「五大堂」
松島のシンボル・五大堂は、807年に坂上田村麻呂が東征のときに建立した毘沙門堂が始まりと云われています。
慈覚大師円仁が延福寺を開いて五大明王を安置したところ、坂上田村麻呂が祀った毘沙門天が光を発して沖合いの小島に飛び去り、毘沙門島になったという伝説があります。
現在の建物は、 伊達政宗が慶長9年(1604)に創建したもので、桃山式建築手法の粋をつくして完工したものです。
五大堂からは、美しい松島湾を見渡すことができます。
 関西/名古屋小牧発!LCCピーチとFDA・SKY&JR秋の乗り放題パスを使って、新潟から日本海・庄内、山形をめぐる観光プランです。初日は庄内鶴岡のSHONAI HOTEL SUIDEN TERRASSEに宿泊。2日目は酒田を観光して天童温泉へ♪3日目は山寺の五大堂から絶景を眺めて仙山線で仙台へ。
関西/名古屋小牧発!LCCピーチとFDA・SKY&JR秋の乗り放題パスを使って、新潟から日本海・庄内、山形をめぐる観光プランです。初日は庄内鶴岡のSHONAI HOTEL SUIDEN TERRASSEに宿泊。2日目は酒田を観光して天童温泉へ♪3日目は山寺の五大堂から絶景を眺めて仙山線で仙台へ。