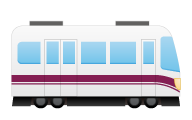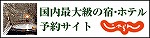この観光プランのおすすめポイント
 日本人の総氏神様を祀る伊勢神宮内宮
日本人の総氏神様を祀る伊勢神宮内宮
五十鈴川の清らかな流れに洗われた広大な敷地に、伊勢神宮内宮(ないぐう)があります。
ご祭神は、天照大御神(あまてらしますすめおおみかみ)です。
伊勢神宮内宮は全国の神宮125社の中で最高位にあり、約二千年前、天照大御神が「うまし国」とお気に召されてご鎮座された神宮発祥の地です。
皇大御神の御神体は、八咫鏡(やたのかがみ)で、八坂瓊勾玉(やさかにのまがたま)と草薙剣(くさなぎのつるぎ)を加えて三種の神器(じんぎ)と呼ばれています。
 伊勢神宮内宮の前に広がる門前町
伊勢神宮内宮の前に広がる門前町
おはらい町は、宇治橋から五十鈴川に沿って約800mの石畳の通りに、江戸時代の商家の風情を残した土産物店や飲食店が立ち並ぶ人気スポットです。
町の中心には、約4,000坪の敷地内に江戸から明治にかけての伊勢路の代表的な建築物が移築・再現された”おかげ横丁”があります。
おはらい町の詳しい情報はこちら
 瀧尾神社
瀧尾神社
瀧尾(たきのお)神社は、大丸創業者の下村彦右衛門も熱心に参拝したことから、金運・商売繁盛のご利益がある神社として知られています。創建は平安時代とも言われ江戸初期、本殿には、辨財天、大黒天、毘沙門天の三御柱の大神様が祀られています。
拝殿天井に全長8mの木彫りの龍が据え付けられています。
江戸時代後期の彫刻家・九山新太郎の作とされ、あまりの躍動感ある姿に当時は「龍が夜な夜な水を飲みに動き出す」と恐れられたため、金網が張られたと言い伝えられています。
 モダンで斬新なデザインの東福寺本坊庭園
モダンで斬新なデザインの東福寺本坊庭園
東福寺は、通天橋の紅葉が有名ですが、本坊庭園のお庭も一見の価値があります。
本坊庭園とは、大方丈の建物の四方に広がる個性的な庭園で、昭和14年に作庭家 重森三玲によってつくられました。
四方向に作られた庭園にはそれぞれテーマがあり、東庭が「北斗七星」、南庭には四つの神仙島、京都五山、須弥山が表現されています。

 西と北の庭は市松模様のデザインで統一され、西庭は井田を表した大市松模様、北庭が苔と板石による小市松となっています。
西と北の庭は市松模様のデザインで統一され、西庭は井田を表した大市松模様、北庭が苔と板石による小市松となっています。
北斗七星、蓬莱、瀛洲、壺梁、方丈、京都五山、須弥山、市松の八つの意匠を盛り込み、これが釈迦の入滅を表す「釈迦八相成道」にもあたることから、「八相の庭」と名付けらました。
従来の日本庭園には無いモダンで斬新なデザインに配置された苔と石のコントラストがとても印象的です。
東福寺本坊庭園の詳しい情報はこちら
 薬師寺
薬師寺
薬師寺は、「法相宗(ほっそうしゅう)」の大本山です。
白鳳時代680年、天武天皇によって皇后(後の持統天皇)の病気平癒を祈願し発願され、697年持統天皇の時代に完成しました。
当時は、その大伽藍はわが国随一の壮麗さを誇り、金堂や塔のたたずまいは「龍宮造り」と呼ばれるほどの美しさでした。
その後、幾多の災害により東塔を除いて失なわれましたが、現在は復興されつつあり、1998年ユネスコ世界遺産に登録されました。
薬師寺の詳しい情報はこちら
 東大寺
東大寺
東大寺は、奈良の大仏さまで知られる奈良時代創建の代表的な寺院で、都である平城京に全国の国分寺の中心として建立されました。
大仏殿は世界最大級の木造建造物です。
天平15年(743)に聖武天皇が生きとし生けるすべてのものが栄えるようにと願い、盧舎那大仏(るしゃなだいぶつ)造立の詔を発し、
天平勝宝4年(752)に大仏さまは開眼されました。以降次々と堂塔が建造され、40年近くかけて伽藍が整いました。
その後、幾度となく戦乱に巻き込まれて焼け落ちましたが、現在の伽藍の多くは公慶上人らによって江戸時代に再興されました。
※奈良市観光協会サイトより引用
 鹿が群れる奈良公園
鹿が群れる奈良公園
奈良公園は、東大寺や興福寺、春日大社といった奈良の見どころが集まる一帯に広がる公園で、約1,100頭の鹿が暮らしています。
鹿せんべいを売っているお店がありますので、せんべいを買って鹿にやることができます。
公園の奥には、なだらかな芝生の若草山、春日山、高円山などの山々が連なっていて、緑豊かないにしえの古都の風情を感じさせます。
 近鉄自慢の観光特急「しまかぜ」「あをによし」、特急「ひのとり」に乗車して伊勢・京都・奈良をめぐるクラブツーリズムのツアーです。初日は伊勢神宮を参拝、京都駅周辺のホテルに泊まります。2日目午前中は京都で自由行動♪奈良に移動して奈良公園を約2時間半散策できます。
近鉄自慢の観光特急「しまかぜ」「あをによし」、特急「ひのとり」に乗車して伊勢・京都・奈良をめぐるクラブツーリズムのツアーです。初日は伊勢神宮を参拝、京都駅周辺のホテルに泊まります。2日目午前中は京都で自由行動♪奈良に移動して奈良公園を約2時間半散策できます。