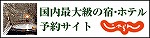この観光プランのおすすめポイント
 「お稲荷さん」の総本宮、伏見稲荷大社
「お稲荷さん」の総本宮、伏見稲荷大社
全国に30,000社あるといわれる「お稲荷さん」の総本宮が伏見稲荷大社です。
奈良時代の和銅4年(711)に御祭神である稲荷大神が稲荷山に鎮座して以来、多くの信仰を集め、五穀豊穣、商売繁昌、家内安全、諸願成就の神として、全国津々浦々に至るまで広く信仰されてきました。
稲荷山の参道に並ぶ約1万基の鳥居が有名ですが、これは願い事が「通る」あるいは「通った」御礼の意味から、鳥居を奉納する習慣が江戸時代以降に広がった結果です。
 松尾大社
松尾大社
松尾大社では、毎年11月下旬から翌年1月末まで、拝殿(東面)に干支の大絵馬を掲げています。
大絵馬は、高さ3.2m、横幅5.5m、厚さ15cm、総重量約90kg余りの超大型絵馬で、京都の版画家故井堂雅夫先生の原画をもとに作成されています。
令和7年(2025年)の干支は「乙巳(きのとみ)」で、大絵馬には川から迫り出る白大蛇が描かれました。
 京都の奥座敷に佇む貴船神社
京都の奥座敷に佇む貴船神社
貴船神社は京都の奥座敷、貴船山の麓に佇む神社で、古くから水の供給を司る神様を祀る神社として、信仰を集めてきました。
歴代の朝廷からの信仰も厚く、嵯峨天皇が生馬を捧げて雨乞いを祈願したことから、絵馬の発祥になったとも言われています。
また、本宮から奥宮へ向かう途中にある中宮は「結社(ゆいのやしろ)」と呼ばれ、縁結びのお社として知られています。
参道は近くを流れる貴船川のせせらぎが聞こえ、神聖な雰囲気が訪れる人に癒してくれます。春日灯篭が連なる石段の参道には青もみじが溢れ、朱塗りの春日灯籠とのコントラストは見事です。
 上賀茂神社
上賀茂神社
京都市の北に位置する、上賀茂(かみがも)神社。正式な名称を「賀茂別雷(かもわけいかづち)神社」といいます。
神社のすぐ側には賀茂川が流れ、神社の裏手には山がそびえるなど、自然豊かな場所にあります。
京都で最も古い神社で、あらゆる災難を除く厄除けの神として信仰されています。
厄除、方除、開運、雷除、災難除、必勝の神様として古くから信仰され、平安時代には「源氏物語」の作者、紫式部も参拝しています。
 境内にある片岡社(かたおかのやしろ)は、縁結びの神様として知られています。
境内にある片岡社(かたおかのやしろ)は、縁結びの神様として知られています。
紫式部の歌に「ほととぎす声まつほどは片岡のもりのしづくに立ちやぬれまし」(ホトトギス(未来の旦那様)の声を待っている間は、この片岡の社の梢の下に立って、朝露の雫に濡れていましょう)と詠まれています。
十二単姿の姫の絵柄の「片岡絵馬」は女性に人気です。
 縁結びにご利益 下鴨神社
縁結びにご利益 下鴨神社
下鴨神社は、鴨川と高野川に挟まれた三角地帯に位置し、境内には緑豊かな糺(ただす)の森が広がります。
糺の森を抜けると、相生神社という縁結びの神さまが祀られています。
ご祭神の神皇産霊神(かむむすびのかみ)は縁結びの神、結納の守護神としてあがめられています。

 すぐ横に2本の木が途中から1本に結ばれる「連理の賢木」があり、縁結びの象徴、紅白のひもでつながれています。
すぐ横に2本の木が途中から1本に結ばれる「連理の賢木」があり、縁結びの象徴、紅白のひもでつながれています。
えんむすびの絵馬に願い事を書いて、縁結びのお社「相生社」の横にある「連理の賢木」の回りを男性は左回りに、女性は右回りに3回廻ってお願いしましょう。

 新春の京都を1泊2日で訪ねるクラブツーリズムのツアーです。個人では行きにくい絵馬発祥の貴船神社や松尾大社など令和8年の干支「午」にちなんだ神社を参拝します。そのほか、京都随一の初詣名所である伏見稲荷大社や上賀茂神社を参拝して、1年の無病息災・家内安全を祈願しましょう。
新春の京都を1泊2日で訪ねるクラブツーリズムのツアーです。個人では行きにくい絵馬発祥の貴船神社や松尾大社など令和8年の干支「午」にちなんだ神社を参拝します。そのほか、京都随一の初詣名所である伏見稲荷大社や上賀茂神社を参拝して、1年の無病息災・家内安全を祈願しましょう。