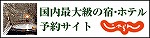この観光プランのおすすめポイント
 萩反射炉
萩反射炉
萩反射炉は、幕末の安政3年(1856)に萩藩が海防強化の一環として西洋式の鉄製大砲鋳造をめざし、試作的に築いた反射炉の遺跡です。
当時は鉄製の大砲を建造するには衝撃に弱い硬い鉄を粘り気のある軟らかい鉄に溶解する必要があり、その装置として反射炉がつくられました。
今では高さ10.5mの煙突にあたる部分が残り、当時の面影を残しています。
平成27年7月、萩の5資産を含む「明治日本の産業革命遺産」が世界遺産に登録されました。
 吉田松陰が主宰した松下村塾
吉田松陰が主宰した松下村塾
松下村塾は、安政4年(1857)に28歳の吉田松陰が身分や階級にとらわれず、子弟を塾生として受け入れた私塾です。
わずか1年余りの間でしたが、久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文、山県有朋、山田顕義、品川弥二郎など、明治維新の原動力となり、明治新政府に活躍した多くの逸材を育てました。
松陰神社の境内に、修復された当時の建物があり、外観を自由に見学できます。
松下村塾、吉田松陰幽囚ノ旧宅は「明治日本の産業革命遺産」として、平成27年7月に世界文化遺産に登録されました。
 萩みかんたけなか
萩みかんたけなか
松陰神社の境内に夏蜜柑菓子のお店「たけなか」があります。
名物は「柑乃雫(かんのしずく)」。
自社農園で栽培した酸味の強い萩みかんの中身をくりぬき、海藻で固めてゼリーに。
再び夏みかんの皮の中に戻し、見た目は夏みかんそのもの!という贅沢なスイーツに仕上げています。
他にも特産の夏みかんを使ったジュースなどを販売しています。
 明倫学舎
明倫学舎
全国屈指の規模を誇った萩藩校明倫館。
萩藩校明倫館は、享保3年(1718年)に5代藩主毛利吉元が毛利家家巨の子弟教育のために堀内に建てた藩校です。
約5万㎡もの敷地内に学舎や武芸修練場、練兵場などがあり、吉田松陰の功績などを、映像やパネル、レプリカで展示しています。
飲食スペースでは日本海で獲れる新鮮な萩のブランド魚などの旬の味覚を、萩の名店「割烹千代」がリーズナブルな価格で提供しています。
萩焼や夏みかんのお菓子などのお土産も勢ぞろい!
明倫学舎の詳しい情報はこちら
 萩の城下町を散策
萩の城下町を散策
萩城城下町周辺には、萩焼を扱うお店がたくさん並んでおり、土産物店や古民家を改装したカフェなど、散策の途中に立ち寄りたいスポットがたくさんあります。
また、着物のレンタルができるカフェがありますので、着物を着て城下町のそぞろ歩きはいかがですか?
まるで江戸時代にタイムスリップしたかのような気分が味わえますよ!人力車での散策もおすすめです。
 明倫学舎
明倫学舎
全国屈指の規模を誇った萩藩校明倫館。
萩藩校明倫館は、享保3年(1718年)に5代藩主毛利吉元が毛利家家巨の子弟教育のために堀内に建てた藩校です。
約5万㎡もの敷地内に学舎や武芸修練場、練兵場などがあり、吉田松陰の功績などを、映像やパネル、レプリカで展示しています。
飲食スペースでは日本海で獲れる新鮮な萩のブランド魚などの旬の味覚を、萩の名店「割烹千代」がリーズナブルな価格で提供しています。
萩焼や夏みかんのお菓子などのお土産も勢ぞろい!
明倫学舎の詳しい情報はこちら
 旧萩藩御船倉
旧萩藩御船倉
旧萩藩御船倉は、藩主の御座船や軍船を格納した船倉で、浜崎重要伝統的建造物群保存地区にあります。
奥行き27メートル、間口8.8メートルの大きな船倉で、天保年間(1830~43)に作成された「八江萩名所図画」には4棟の船倉が描かれており、もっとも大きかったものが現存しています。
屋根を葺いた旧藩時代の船倉としては全国唯一の遺構で、国の史跡に指定されています。
旧萩藩御船倉の詳しい情報はこちら
 赤・青・緑のコントラストが美しいパワースポット
赤・青・緑のコントラストが美しいパワースポット
元乃隅神社(もとのすみじんじゃ)は、昭和30年に、地域の網元であった岡村斉(おかむらひとし)さんの枕元に白狐が現れ、「これまで漁をしてこられたのは誰のおかげか。」と過去からの関わりを詳細に述べた後、「吾をこの地に鎮祭せよ。」というお告げがあったことにより、建てられました。
商売繁盛、大漁、海上安全は元より、良縁、子宝、開運厄除、福徳円満、交通安全、学業成就、願望成就の大神です。
昭和62年から10年間かけて奉納された123基の鳥居が、龍宮の潮吹側から100m以上にわたって並ぶ景色は圧巻です。
神社敷地内にある高さ約6mの大鳥居の上部には賽銭箱が設置されており、見事、賽銭を投げ入れることができたら願い事が叶うと言われています。
※ながと観光なび「ななび」から引用
 「日本の橋ランキング」で1位の角島大橋
「日本の橋ランキング」で1位の角島大橋
角島大橋(つのしまおおはし)は、世界最大級の旅行口コミサイトサイト「トリップアドバイザー」が選んだ「日本の橋ランキング」で1位に輝いた国内有数の景勝地です。
コバルトブルーの海に向かって真っすぐに伸びるはまるで海外のリゾート地のよう。
全長1780mにも及ぶ橋は平成12年11月に開通。
離島に架かる橋のうち、無料で渡れる一般道路としては、日本屈指の長さを誇ります。
※ながと観光なび「ななび」より引用
 長門湯本温泉
長門湯本温泉
長門湯本温泉は山口県内の温泉地の中でも最も古く、その歴史は室町時代に始まり、江戸時代には藩主も度々湯治に訪れていたという歴史ある温泉です。
泉質はアルカリ性単純温泉で、無色透明。アルカリ度はかなり高く、肌にやわらかな湯で、化粧水成分に近く「美肌の湯」ともよばれています。
※写真は山村別館の大浴場
 瑠璃光寺(五重塔は令和の大改修中)
瑠璃光寺(五重塔は令和の大改修中)
山口市の瑠璃光寺(るりこうじ)は、大内氏が全盛の戦国時代に大内義弘の弟が建立しました。
瑠璃光寺の五重塔は、奈良の法隆寺、京都の醍醐寺の五重塔とともに日本三名塔に数えられ、檜皮葺き総檜造りの優美な姿は、室町時代中期における最も秀でた建造物と言われています。
瑠璃光寺五重塔は約70年ぶりの檜皮葺屋根の全面葺き替え工事中で、令和8(2026)年3月までの間実施されています。
五重塔は現在改修の為、シートで覆われており見ることができません。
詳しい情報はこちら
 禅味あふれる日本庭園「常栄寺雪舟庭」
禅味あふれる日本庭園「常栄寺雪舟庭」
瑠璃光寺五重塔などがある山口市市街の少し奥にある常栄寺(じょうえいじ)は、元は大内政弘が約500年前に建てた別荘で、庭は雪舟につくらせたものといわれています。
山林を背景に心字池や枯滝、立石を巧みに配し、雪舟の水墨画の世界を思わせる趣ある庭園です。
本堂に座って目の前に広がるお庭を見ていると心が落ち着き、嫌なことも忘れられます。
雪舟庭は禅味あふれる日本庭園の代表作として、国指定の史跡および名勝になっています。
 日本屈指の大鍾乳洞「秋芳洞」
日本屈指の大鍾乳洞「秋芳洞」
秋吉台国定公園の地下100m、その南麓に開口する日本屈指の大鍾乳洞「秋芳洞(あきよしどう)」。
ひんやりと肌をさす冷気漂う杉木立を通り抜けると、秋芳洞の入口です。洞内の観光コースは約1km(総延長は10.7kmを越え国内第2位)、温度は四季を通じて17℃で一定し、夏涼しく冬は温かく、快適に観光できます。
時間が凍結したような不思議な自然の造形の数々は変化に富み、私たちの心に大きな感動を呼び起こさせてくれます。
※山口県美祢市秋吉台国定公園観光情報より引用