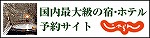この観光プランのおすすめポイント
 高松城跡・玉藻公園
高松城跡・玉藻公園
玉藻公園は讃岐国領主・生駒家、高松藩主・松平家の居城だった高松城跡を整備した公園です。瀬戸内海の海水をお堀に引き込んだ城は日本三大水城として知られ、園内には国の重要文化財に指定されている艮櫓、月見櫓、水手御門、渡櫓、披雲閣があるほか、国の名勝に指定されている披雲閣の庭園があります。
※うどん県旅ネットより引用
 丸亀城
丸亀城
丸亀城は石垣の名城として全国的に有名で、石垣は”扇の勾配”と呼ばれる特徴的な美しい曲線を描いています。
400年の時を経た今日でも決して色あせることなく、自然と調和した独自の様式美をはっきり現在に残しています。
天守は全国に現存する木造天守十二城の一つで、重要文化財に指定されています。
毎年3月下旬〜4月上旬に丸亀城桜まつりが開催され、たくさんの花見客で賑わいます。
丸亀城の公式サイトはこちら
 江戸時代の姿を今に伝える高知城
江戸時代の姿を今に伝える高知城
高知城は、関ヶ原の戦いの功で土佐24万石に封ぜられた山内一豊が、慶長6(1601)年から築いた平城です。
享保12(1727)年の大火でほとんどが消失しましたが、宝暦3(1753)年に再建されました。
全国でも唯一、本丸の建造物が江戸時代のまま現存する貴重な城郭です。
天守など15の建造物が国の重要文化財に指定されています。
 松山市の中心部にそびえる松山城
松山市の中心部にそびえる松山城
松山市の中心部、勝山(標高132m)にそびえ立つ松山城は、賤ヶ岳(しずがたけ)の合戦で有名な七本槍の1人、加藤嘉明が築き始めたお城です。
門・櫓・塀を多数備え、狭間や石落とし、高石垣などを巧みに配し、攻守の機能に優れた連立式天守を構えた平山城と言われております。
松山城は、日本で12か所しか残っていない「現存12天守」のうちのひとつ、江戸時代以前に建造された天守を有する城郭の一つです。平成18年に「日本100名城」、平成19年には道後温泉とともに「美しい日本の歴史的風土100選」に選定されました。
※松山城のホームページから引用
松山城へは、路面電車を「大街道」駅で下車し、お土産屋さんが並ぶ通りを東雲口まで歩いて、ロープウェイまたはリフトで長者ヶ平まで上ります。
 今治城
今治城
築城の名手と名高い藤堂高虎が築いた今治城は、築城当時は三重の堀をめぐらし、強固な舟入(港)を備えた日本最大規模の海城でした。
今では城の中心部の堀と石垣がほぼ完全に遺り、復興された天守や櫓、城門が美しい姿を見せています。
天守最上階の展望台からは瀬戸内海の絶景が広がります。海水が出入りし、魚が回遊する巨大な堀も見どころです。
今治城のホームページはこちら
 築城の名手高虎、会心の名城「宇和島城」
築城の名手高虎、会心の名城「宇和島城」
現在の地に初めて天守が建造されたのは慶長6年(1601)藤堂高虎(とうどうたかとら)築城のときとされています。城の外郭は上から見ると不等辺5角形をしており、随所に築城の名手と言われた高虎ならではの工夫が見受けられます。
高虎が今治に転封となってのち、奥州仙台藩主、伊達政宗の長子秀宗が宇和郡10万石を賜り、元和元年(1615)に入城。2代宗利の時、天守以下城郭の大修理を行い、寛文11年(1671)に完成。その姿を現在に残しています。
※宇和島市観光物産協会のホームページより引用
 大洲城
大洲城
大洲城(おおずじょう)は、明治21年(1888)には天守も取り壊されましたが、4棟の櫓は解体をまぬがれ、いずれも国の重要文化財に指定されています。
城跡も県史跡に指定され今日も大切に保存されています。
4層4階の天守は、明治期の古写真や「天守雛形(ひながた)」と呼ばれる江戸期の木組み模型など豊富な資料をもとに平成16年(2004)に木造で復元したものです。
重要文化財の台所櫓、高欄櫓とL字型に多聞櫓で連結し、複連結式天守と呼ばれる構えを成しており、これら全ての建物を観覧することができます。
※大洲市観光協会のホームページより引用